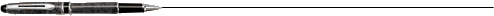|
第四巻(第三十一段〜第四十段) |
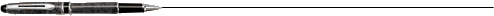
 |
第三十一段 |
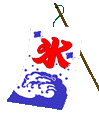
夏の必需品(?)に、いわゆる制汗デオドラント商品がある。さまざまな種類とコピーが鎬を削っている。いわく、「汗のニオイをおさえます」「汗をおさえます」「わきの下サラサラ」「わきの下の汗そのものをおさえます」なるほどなるほど。あれ?でも汗の働きってなんだったっけ?蒸発によって体温を下げるじゃなかったかな?だったら、それ出なくしてよかったんだろうか?どんどん暑くなって・・・体温調節機能が働かなかったら、間違いなく熱中症。でなくても、暑くて暑くてたまらんってことにならないのかな。(2001,8,9) |
 |
第三十二段 |

夏の不思議な思い出。学生の頃、バイトである神社のお祭を手伝った。その神社の背後に山があって参道に無数の灯篭があり、参拝した人たちが夜、その灯篭に火を入れて歩くお祭で、のぼりを立てていくつかに分けたグループの先頭を歩くバイトだった。ペースが遅いので待ちきれずどんどん歩いていくうちに気が付くとひとりになっていた。周囲は竹やぶと崖で、真っ暗だった。「あれれ、ここは?」と思ってると「どうしたんですか?」という声がして、振り向くと浴衣を着た女性がにこにこ笑っていた。道がわからないことを言うと「あそこに灯りが見えるでしょ。あっちのほうへ歩いていくと帰れますよ。」確かに灯りが見える。「ありがとうございます。」と言って振り向いたとき、そこには誰もいなかった。その時は「あれ?」ぐらいのもので無事帰れたのだが、道々あれは誰でどこから現れてどこへ消えたのか・・・考えれば考えるほど怖くなってきて、帰ったときには汗びっしょりだった。もう、随分まえの話だ。(2001,8,14) |
 |
第三十三段 |

これは冬の話。彦根のある山に洞窟があるらしいと聞いてひとりで出かけた。バスを降りて山に入ると想像以上に雪が積もっていて、やがて腰を超える積雪となった。一歩を進めるのも大変で、足を引き抜くのも一苦労。体力はどんどん消耗し、見渡す限りの雪の中で腰を降ろすこともできない。しかも完全に一人きり。その時突然、急激にはらがへってきた。これまでに経験したことがないような異様な空腹。冗談ではなく、もう死ぬんじゃないかと思った。その時、カバンの中にお土産に買ったまんじゅうがあることを思い出し、むさぼるように食った。その瞬間、その恐怖を伴うような空腹は跡形もなく消え去った。結局洞窟は探せずに帰ったのだが、数日後『日本妖怪大事典』に、ヒダル神というのを見つけた。昔、峠で餓死した旅人の霊が妖怪になったもので、そこを通る旅人にとりついて餓死さそうとするらしい。まさに・・・これだ、と思った。助かるためには何か食べればよい、何もないときは手のひらに「米」と書いて飲めばよいとあった。(2001,8,14) |
 |
第三十四段 |
|
「そこに山があるからだ」という言葉があるが、「どうしてくそ暑いのに、クーラー効いた車じゃなくってバイクなの?」と聞かれたら、やはり「そこに魅力的な道があるからです。」と答えることになるだろう。それほどに、バイクは、ただ走ることがイイ。今年もそんな道を求めて出発した。高速に入って、徐々にスピードに体のあらゆる部分が慣れてくると、頭の中がすうーっと透明になり、目は瞬きの回数が極端に減る。吹き抜けていく風が、いろんな俗っぽい部分を全部洗い流してくれる。何も考えない快感、自分がふっとなくなる快感・・・とてもイイ。高速を降りて、誰も通らないような古い狭い峠を走る。200kgを越すバイクにはちょっとつらいんだけど、一生懸命走る。その自分しか知らない一生懸命感に酔いながら。やがてバイクは山間のある温泉宿に着く。湯屋温泉の奥田屋というこじんまりしたいい雰囲気の旅館だ。ぬるめのお湯にひとり四肢を伸ばし、しばしぼおーっとする。至福のときだ。浴衣を着て部屋に戻り、はじめてすぐ横を川が流れてることを知った。せせらぎの音とともに涼しい風が入ってくる。外はいつしか煙るように雨が降っていた。 |
 |
第三十五段 |
温泉宿の朝食は素敵だ。人生頑張って来たよなーて感じの人たちが、浴衣でとりとめのない話をしながら食べている風情が好きだ。なかでも、もと会社役員風の3人連れが「あいつを連れてきてやれば・・・」なんて、奥さんの話をして笑いあってるさまは、ほんとうに『いとをかし』だった。さてそろそろ、と宿を出た。雨上がりの涼しい空気の中、御岳を目指してひとつひとつコーナーを越えていく。そのつど、新鮮な景色が目の前に現れる。濁河峠から野麦峠へ。ときどき雨がぱらつく。天気がよいときれいに乗鞍が見えるのだが、あいにくの曇り空でまったく見えない。それどころか山頂は雨かもしれない。まっいいかと思いつつ気持ちのいい白樺林の中をしばらく走ると四つ角に出る。左が乗鞍岳山頂への道だ。ようし、頑張ろう!心を決めて出発する。道はずんずん高度を上げていく。そして風景が地球離れしてくると、いよいよ山頂である。荒涼という言葉がいちばんしっくり来る風景が見渡す限り広がっている。何度来ても、いつもここは新鮮だ。小雨まじりの強い風が吹き、かなり寒い。少し休んでスカイラインを下る。とたんに濃霧と強い雨。怖い。ただひとり、見知らぬ星を走っているような気になる。とても太刀打ちできない自然の力を感じる瞬間だ。こうなるとあとは我慢ということになる。まして10度を越える急坂、ヘヤピンの連続。ふもとについたときにはぐっしょり、だ。それでも高山に着いた頃にはすっかり乾いて、空は夕方の色を少し含んだ青空が広がっていた。すこし早目の夕食を食べて高速に乗れば、今日じゅうには帰れるだろう。 |
 |
第三十六段 |

子供の頃、夏はセミとともに始まり、セミとともに終わった。子供はみんな長い長い梅雨が嫌いで、7月の声を聞くと、早く夏になってほしくて居ても立ってもいられなくなる。そんな時、何かのはずみでニイニイゼミの声を聞くと「ああ、夏だ!」と直感的に感じるのだ。そして夏休み、涼しい朝はクマゼミの声とともに始まり、昼を過ぎてぐんぐん気温が上がるとそれはアブラゼミの声に変わる。その鳴き声はまさに「あちぃーーー」と聞こえたものだ。山深い親戚の家ではミンミンゼミの声とともに野山を駆け回り、ヒグラシの声にせかされるように家路に着いた。やがて8月も後半になると、そこここにセミの亡骸が見られるようになる。セミが7年も土中で過ごすことを理科で習ったことも思い出して、子供ながら「命・・・」なんてことを感じたりするのだ。そして、ツクツクボウシが鳴きだすと、もうゆっくりはしてられない。残った宿題を片付けないと大変だ。昔の人はツクツクボウシの声を、逝く夏を惜しむ「つくづく、惜しい。」と聞いた。誇るべきセンスだ。今の子供たちも、セミとともに夏を過ごしてるのだろうか。(2001,9,9) |
 |
第三十七段 |
|
どうも日本にはまだまだ黒舟をひきずっているようなところがある。英語圏人コンプレックスとでもいうか。もうそろそろなんとかなってもよさそうなものなのにな。でも、英語で言うとカッコいい。英語の名前なんか、やっぱりカッコいいなあと思ってしまう。俳優の名前もスポーツ選手の名前も。よく考えるとどうってことないんだけど。タイガーウッズなんか、林のトラさんなのに・・・。(2001,9,9) |
 |
第三十八段 |
ずいぶん前の新聞記事の話。西田哲学で有名な西田幾多郎氏の「自分は人生の前半を教室で前を向いて過ごし、後半を後ろを向いて過ごした。教室の中でくるりと一回転したのが自分の人生だ。」というような言葉をもとに、「教師というのはその一生を教室という狭い世界で過ごす。そんな狭い世界しか知らない教師に、本当に子供の様々な可能性、将来の進みうる道が指導できるのだろうか?」という問題提起があった。読んで、それこそハンマーで後頭部をグワアーンと殴られたような衝撃を受けた。本当にそうだ、と思った。多くの教師は大学まで教室で学生として過ごし、採用されるとやはり教室で教師として過ごす。教師と生徒という実社会ではあまりない人間関係の中で、ずううーっと過ごすわけだ。だから、教師の常識は世間の非常識なんてことを言われたりするのだ。そのあたりをちゃんと認識せねばと思いつつ、今日もうろうろしている。(2001,9,9) |
 |
第三十九段 |
|
もうすぐ時代祭だ。学生の頃、時代祭の行列のバイトは人気があって、ずいぶん朝早くから並ばないと当たらなかった。祭当日は朝早くある小学校に集合してくじで衣装を決めて着替え、貸切バスで御所へ向う。何の前触れもなく鎧武者を満載したバスに並ばれるというのは、他のドライバーにはかなりの驚きであったようだ。さてその年ひいたくじには「ほら貝」とあった。「ほら貝を持って歩いてくれたらいいから。」世話役の言葉に安心して午前中は御所で待機していると、近くの小学校の子供たちが「生きた」歴史の授業って感じでやってくる。先生いわく、「はーい、みなさーん、ここにいるのが昔の人たちですよー!」・・・違うって!と思いつつ、ひとしきり好奇の目にさらされる。サインを求める奴には「徳川家康」とかてきとうに書いてやる。そして、出発の時間。御所の中のメインストリート、両側に固唾を飲んで見守る満員の観光客、やぐらの上に各局のテレビカメラ。これ以上ない晴れがましくも緊張の瞬間。その時、もう一人のほら貝が貝を口にあてた。「えっ?」と思うまもなく「ブォオオオオー!」とやった。ワアー!というものすごい歓声とどよめき。太鼓が「ドンドーン!」とやった。なぜかワアー!の歓声。そして・・・すべての人の視線が自分に集中する。この一瞬の長いこと。しようがない、貝を口にあてる。「スウウウウウー!」そして、ドオオオー!という大爆笑。その瞬間、頭の中でなにかが弾けた。その後、「ブオオオー、ドンドーン、スウウー、ドオオー!(爆笑)」という世にも不思議なリズムが都大路を3時間にわたって練り歩いたのだった。その日の観客動員数14万人。14万人に笑われる経験って、ちょっとできない。次の年の秋のある日の新聞に山伏がほら貝を吹いている写真が載っていた。「今年から時代祭ではほら貝を吹くのに本当の山伏を雇いました。」と書いてあった。(2001,9,24) |
 |
第四十段 |

最近のおこちゃまは・・・体を直立状態にしておくということが、なかなかできない。立っていられずにどこであっても座り込む。イスに背筋を伸ばして座ることも苦手だ。机の上に上体をべたあっと預けてしまう。だから、もたれられる所にズベっと座る。可能な所ならズベラアっと寝転んでしまう。これを世の大人たちは「だらしない。」とか「最近の子供は。」などとモラル論で片付けているが、そんな簡単なことじゃない。これは、ヒトの進化の逆をたどっているということにはならないだろうか。水から上がった原始生物が地上をはい、4本足で歩き、座る(しゃがむ)ことで手を使うことを獲得し、やがて直立して頭を全身で支えることで脳を飛躍的に発展させ・・・そしてできたのがヒト。子供とは、生物としてのヒトの最新型個体。それが逆の矢印を指向するようになったということは、進化が一つのピークを超えて下降線をたどっているということである。と、するならこれはヒトの『生物的危機』である。このままではヒトはやがて、海中に戻ることになるかもしれない。クジラのように。(2001,10,11) |