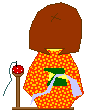|
第八巻(第七十一段〜第八十段) |

 |
第七十一段 |
|
「あっしには関わりのねえことでござんす。」と聞いてもピンと来る人はもう少ないかもしれない。これこそ股旅物のヒーロー木枯し紋次郎の決めセリフである。白黒TVの前にちょこんと座って画面に見入っていたちびの自分がいる。再放送だったかもしれない。かっこいい!文句なしにかっこいい!ふろしきを合羽に串カツ用の楊枝をくわえて、気分はすっかり紋次郎。正義の味方というのではない。人が困っていても積極的に関わるわけじゃない。決して徒党を組まない。だが、知らないうちに騒動に巻き込まれ、頼られ、どうしても許せない状況に追い込まれ、そしてぎりぎりで勝つのだ。そして「ごめんなすって・・・」と去っていく。そこに毎回同じナレーションがかぶる。「木枯し紋次郎、上州新田郡三日月村の貧しい農家に生まれる。十歳のときに国を捨て・・・」小さくなっていく後ろ姿。かっこいい!たまらん!その頃から上州新田郡三日月村は、絶対に行ってみたい場所となった。架空の場所とわかっていても・・・。そして、なんと先日ネットで三日月村を見つけたのだ!そこはまさに上州新田郡。小説をもとに紋次郎の世界を再現させた村なのだ。ひさびさに血が騒いだ。行かねば!ひかり号と東武鉄道を乗り継いでいった。前の晩はすぐ近くの藪塚温泉に泊まった。素朴なのんびりした温泉だ。客は自分を入れて4人だった。次の朝、雨上がりの上州はもう気分満点だ。そして三日月村、入り口で昔のお金に両替して入村、紋次郎気分ですする山菜そばとどぶろくの値段を婆ちゃんが「十文ね。」とぶっきらぼうに言う。あとは「待ちやがれ!紋次郎!!」と敵が現れたら言うことないんだけどな。それにしても・・・ひさびさに子供の頃の血が騒いだ。「それだけの理由でそこまで行ったの?」人は言うかもしれない。衝動で旅をするのは・・・そう、「ただの癖ってもんでござんす。」(2002,4,9) |
 |
第七十二段 |
|
小さい時の1年に比べて、大人になってからの1年というのはすごく短い。あっという間に1ヶ月や2ヶ月は終わってしまうし、気が付けば「あらら今年も・・・」ということになる。そしてそのスピードは年とともにますます速くなっていく気がする。そんなことを仲間うちで喋ってた時、W君という人が言った。「5歳の時の1年は人生の5分の1やからな、長いんや。30歳の時の1年は人生の30分の1やから短いねん。」――ほおおー!と思った。まったくそのとおりだ。目からうろこが音を立ててばらばら落ちた。もしかするとこの男・・・ただもんじゃない。(2002,4,12) |
 |
第七十三段 |
「葛の花踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり」 |
 |
第七十四段 |

とっても欲しいものがあって、ついにそれを買いに行った時、同じように見えて3000円と5000円のものがあると、ぱっと3000円に飛びつかないのはなぜだろう。同じものなら安いほうがいいに決まってるのに。どっちかというと5000円のほうが欲しくて、2000円分の納得するための理由が欲しくなってしまう。これがカップラーメン程度のものなら迷わず安いのを買うのだが。本当に欲しい物ほど、高い物ほど、より高いほうを求めてしまう。とするならば、物の値打ちっていったいなんなんだろう?どのくらいわかって買ってるんだろう?てことになる。高い=良いという信仰(?)は根強い。その物の本当の値打ちより、いくらの物ということが重要な決め手となっている。いわゆるブランドものはその典型だ。呉服屋の知人に訊いたことがある。「着物って売れなかったらやっぱりバーゲンするの?ある程度下げても儲かるよなあ。」「いやいや、値段下げても売れへんよ。逆にするんや。」「・・・?」「20万で売れんかったら40万にするんや。すぐ売れるわ。いくらの着物っていうのが値打ちなんやから。」これもまた、目からウロコの話だった。(2002,4,21) |
 |
第七十五段 |

学生の頃、4日かけて木曽路を歩いたことがある。中仙道にあこがれ、木曽にあこがれ、紋次郎にあこがれて、民宿だけを決めて25000分の1の地図に旧道をマークして。1日約20kmをあちこち見ながらてくてく歩く。なかなか目的地に着かない。時はどんどん過ぎていく。この峠の向こうに・・・と思えば、また峠が現れる。汗びっしょりになって歩く自分を道端の名もなき花が、道祖神が、鳥のさえずりがなぐさめ、励ましてくれる。日も暮れかけて、やっと目指す宿場町に着き、民宿の明かりを目にした時の喜びは格別だ。2泊目は日がとっぷり暮れても宿に着かず、真っ暗な国道をとぼとぼ歩いた。右も左も真っ暗で虫の声だけが聞こえてくる。ごくたまに轟音をとどろかしてトラックが通り過ぎていく。そのヘッドライトの光が、瞬間、右も左も見渡す限りの墓地を照らし出した時の恐怖を何に例えれば良いだろう?そして3泊目の夕暮れ、妻籠宿にたどり着いたときの旅情と言ったら・・・もう、なんとも言えない。すっかり江戸時代の旅人気分だ。4日間フルに旅を満喫した。数年後、そんな木曽路が忘れられなくてツーリングの帰りにバイクでその行程を走ってみた。なんと、2時間で通り過ぎてしまった・・・。現代人はスピードと引き換えに、とても大切な物を置き去りにしてきたのかもしれない。(2002,4,24) |
 |
第七十六段 |
|
山の中のある街で小さな中華料理屋に入った。メニューの中に「スブ鶏」というのが・・・。予想はついたんだけど、オネ―サンに聞いてみた。「あの、これなんなんですか?」「酢豚のぉ、豚の代わりに鶏がはいってるんですう。」や、やっぱり。でも酢豚って、ス+ブタじゃなかったっけ。スブ鶏っていったい・・・。訊いてみると、オネ―サンは「んふふふっ。」と謎の微笑を残して去ってしまった。(2002,5,10) |
 |
第七十七段 |
|
某オミズの女の子との会話。「君さあ、怖い話ってどうよ。」「全然大丈夫だよ。わたし見えるもん。」「え?」「この前もさあ、友達と車で走ってたらおじいちゃん立っててさあ、『きゃはは、おじいちゃん立ってる―!』『え、生きてる?死んでる?』『あはは、死んでる―!』みたいな・・・。」「ええ?(冷や汗)」「けっこうさあ、お客さんでもいろんなのしょってるよぉ。この前なんかさ、狐しょってる人いたしねー。あらあら、みたいなかんじね。ふふふ。」「えええ?(かなり冷や汗)」「悪いの背負ってる人は、やだねーやっぱ。あんまり近づかないようにするけど。そういう人ってぇ、向こうからもあんまり近づいてこないんだよね・・・。」こちらをじーっと見つめて事も無げに楽しげに話すその子は、あまりにも怖い。(2002,6,5) |
 |
第七十八段 |
|
広島の比婆山中にある庄原という街に出かけた。四方に緑を感じる落ち着いた静かな街だ。夕食後、日の暮れた街に出て驚いた。車が1台も走ってない。人が1人も歩いてない。と言うより、人の気配そのものがないのだ。自分たちの歩く足音だけがやたら響いて聞こえる。まるで映画のセットのようだ。闇に沈む祠はなにやら不気味で、石屋さんの前に立つ石のドラえもんさえちょっと怖い。そのうちふと、昔、子供の頃の夜はこんなふうだった、と思い出した。夜は暗く、人々は店を、戸を閉ざして眠りに就いたのだった。夜の戸外は、例えば「鬼は外!」と追い出された鬼や、その他の魑魅魍魎の支配する世界だったのだ。いつの頃からか都会人は便利さを求めて夜を侵食するようになってしまった。昼と夜のバランスの崩壊が人の生活そのものの崩壊を呼んでしまったような気がする。朝が来て、街には当たり前のように車が走り、急ぎ足に人が歩いていた。(2002,6,5) |
 |
第七十九段 |
|
祇園祭といえば、17日の山鉾巡幸がクライマックスで、それで終了と思う人が多い。しかし、神事としての祭はむしろその後の神輿の出発から始まるのだ。17日の夕方八坂神社を出発した3基の神輿は、氏子の町を練り歩き夜遅く歓喜の中お旅所に着く。そして24日夜、神輿は汗にまみれた男たちとともに神社に帰ってくる。この時の熱狂と興奮こそが、実は祭のクライマックスなのだ。神社の境内は誇りに満ちた神々しい男たちに埋め尽くされ、おそらくは彼らの大切な女や子供たちがうっとりとその姿を見つめる。そして何度も繰り返される掛け声と拍手と歓声と・・・。その中で神輿はまるでラグビーのスクラムのように拝殿に押し上げられ、男たちの怒号と掛け声の中で興奮は最高潮に達する。男たち、女たち、少し離れたところにたたずむ舞妓と旦那衆、そんな様々な人たちが興奮の中で一つになる。これが、祭だ。京都の、祇園の祭だ。その後やさしく迎える女たちのところへ戻ってくる男たちはみんなとってもいい顔をしていた。(2002,7,29) |
 |
第八十段 |

男6人で、喫茶店でケーキを食べた。本当はかき氷が食べたくて岡崎のとある店に入ったのだった。そこには上品なおじいさんとおばあさんがいた。「氷はございません。ケーキならあります。うちのおいしいのは、タルトタタンです。」有無を言わさぬおばあさんの言葉に、「じゃあそれと、グレープフルーツジュースを・・・」と言いかけると、「ケーキにジュースは合いません。コーヒーか紅茶にしてください。」とぴしゃり。「じゃあアイスコーヒー・・・」で許可してもらった。「砂糖は入れないでください。」「・・・はい。」そのうちタルトタタン様が来た。アップルパイのリンゴがたくさん積み重なって暖かい。そんなケーキだ。たしかにおいしい。なんでも、コンクールで日本一になったのだそうだ。タタンホテルの姉妹の失敗作からできたケーキ・・・とか書いてあった。とりあえず、おいしくて緊張する店だった。(2002,7,29) |