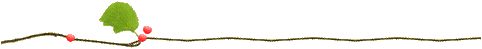|
第十三巻(第百二十一段〜第百三十段) |
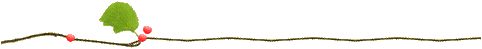
 |
第百二十一段 |
全世界の愛玩犬たちよ、犬としての誇りはあるか |
 |
第百二十二段 |
|
信号待ちで車止めた日曜の昼下がり |
 |
第百二十三段 |
TUNAMI・・・大変。列強こぞって金・金・金・・・。5億出します。6億出します。10億出します。50億出します。でもなんのため?うちの国はこんなにダセルヨ!どうだ、マイッタカ!いやいや、うちこそ世界一ダロ?ヤバイよ、ヤバイよ、今出さないとなに言われるかワカンナイヨ!ほらほら、ほらほら。で、現地混乱大混乱。ワタシ個人でもこれだけだせまーす、ホイ!ボクモ出すよ、ヨイショ!なんかすっきりしない。なんか違うんちゃう?究極はヨンさまが出したと聞いてうちもわたしもと出したというおばちゃん達。ヨン様にプレゼントじゃないからね!あんたらのお子さん、コンビ二弁当ちゃうやろね。あんたら考える優先順位間違ってますから。国連がきちんとリーダーシップとらないかん。で、国ごとの割り当て決めて、それ以外の勝手なあるいは売名的援助は禁じる。で、現地でも混乱しないようシステム作る。本当に効果的に使われるように。しっかりしろ、世界!(2005.1.13) |
 |
第百二十四段 |
|
退屈な毎日が続くと
|
 |
第百二十五段 |
|
「おもしろうてやがて悲しき」もの、それは飛行機。何を今さらと言うだろうけど、実感なんだなーこれが。飛行機はいつも日常から非日常の世界へ連れて行ってくれ、そしてその夢の世界から現実の世界に否応なしに引きずり戻す。帰りはいつも夕方だから、すっかりセピアなモードで乗り込み、まさに後ろ髪を引かれるような思いで雲の上に出ると、まだまだ明るかったりして「ああ、まだ終りじゃないんだ!」と思うのも一瞬の幻で、金色に輝く雲の海に太陽はゆっくり沈んでいき、その後にはこれでもかっていうぐらいの深い深い闇が全てを包み込むようにやってくる。まさに宇宙的な絶対的な暗黒である。それは旅の終りの宣告。もはや逃れようがない。あの夢のような時間は二度と帰ってこない。ああ・・・。そんな思いで眺めている窓にやがて大阪の夜景が広がり、機体は軽いショックとともに伊丹空港に着陸する。荷物の受け取り口に並ぶ頃にはようやく日常モードが機能を取り戻し、心と身体をコントロールしだす。さーて、明日から仕事だ。 |
 |
第百二十六段 |

「ふざけんな、こら!」というのが、いわゆる「できる」と言われる人に対する気持ち。特に同業の「できる」人に対してはまちがいなくこれ。絶対に素直に認めたくない。「なんぼのもんやねん!」である。「あはは」とにこやかに会話してても心から笑ってなんかいない。「負けるか!」と思っている。だから、その人の言動は絶対見逃さないように見ている。なぜ、「できる」のか、自分とどこが違うのか。でも、絶対に真似はしたくない。自分は自分のやりかたでやる。だからといって誰かがその人をよく知りもせず批判したりすると、これまた「ふざけんな、こら!」と思う。「おまえどれだけわかって言うてるねん!」と。「おまえが言うな」と。反骨の精神なのか、天の邪鬼なだけのか、それはわからないけどね。 |
 |
第百二十七段 |
|
春まだ浅い2月末のぽっかり予定のあいた日曜日。旅気分を味わいたくて京都駅から東へ向かう列車に乗り込んだ。米原で乗り換え、さてどこまで行こうかと窓を見ているとなんともきれいな風景が広がり、つい誘われるように下車した。そこは醒ヶ井という駅だった。中仙道の宿場町でもあるその町は真っ白な息吹山を背景に静かにそこにあった。いかにも宿場町らしい町はあくまで静かで美しく、通りに沿ってなんとも見事に澄んだ川が流れている。しばらく歩くと、流れの中ほどにこんこんと水が湧き出しているところがある。醒ヶ井の地名の元にもなり、かつてヤマトタケルがその水を飲んで生気を取り戻したという湧き水である。なんと清らかな水であろうか。感動的ですらある。そして、おいしい。ごく自然に話しかけてくれた老人が、町の人々がいかにこの流れや自然を大切にしているかを語ってくれた。なるほど、と思う。この人影もまばらな静かで美しい町は、町の人々みんなの愛にまるごと守られているのであった。そして、遠く伊吹の雪はこれまた感動的に白かった。 |
 |
第百二十八段 |
|
「次の宿場まで歩いてみぃはるかい?」とその人は言った。「昔で言う1里、まあ4kmぐらいですがなあ。国道歩かんでもな、モーテルのわきから旧中仙道がずうっと残ってますねや。」天気もよいので柏原まで歩くことにした。街道は古い松並木が残ってたり、暗い杉の林の中にスポットライトのような日差しを浴びてただ1本、梅が満開だったりと、飽きることがない。2月とはいえ、少し汗ばむ道のりである。こんな時に口ずさむのは、決まって「木枯らし紋次郎」の歌だ。やがて柏原に着いた。ここは日本一のもぐさの町だそうだ。江戸時代はいくつも専門店があって、大いににぎわったそうだ。今は往時の賑わいはないが、広重の絵にも描かれている亀屋佐京もぐさ店がそのままある。そして店を覗き込むとギョッとする。薄暗い中に座高2mはあろうかという福助が座っているのだ。これが福助人形の元祖だそうだ。福助さんはとても商売熱心なこの店の番頭さんだったそうで、彼の死後もその業績を偲んで人形を置いたそうだ。その様子は前述の広重の絵にも描かれている。その話を京都の伏見人形屋が聞いて、作って売り出したところ、爆発的に売れ、現在に至ってるそうだ。へー!!である。 |
 |
第百二十九段 |

お土産を買うというのも旅の楽しみの1つだが、土産というものには2つの種類があるように思う。1つはその土地の特産品、そこへ行かないと無い物である。北海道の毛蟹であったり京都の八つ橋であったり地方の地酒であったりがそれ。もう1つはそこへ行ってきたということがわかりさえすればよいという、いわば滞在証明書のごとき物である。どこへ行っても必ずある通行手形や「○○へ行ってきました!」という類のまんじゅうがその代表選手である。ま、そこへ行ったことさえわかればよいから、その土地で作っているということより、地名なんかがしっかり入ってるほうがありがたい。だから沖縄限定黒糖ハイチューが大阪で製造されていてもそんなに目くじら立てようとは思わない。でもなあ・・・と思う。昔、知り合いのおっちゃんは「わしは全国の土産作っとんじゃあ。」と言って胸を張っていた。彼の内職は、アパートにこもって、かわいい巾着に北は宗谷岬から南は沖縄までの地名を書いたプレートをくっつけるというものだった。ちょっと・・・やりすぎやろ。(2005.5.17) |
 |
第百三十段 |

動物保護はたしかに大切なことで、無論異を唱えるつもりはないのだけれど、でもね、と思うのだ。現在の生態系というのは、生物の発生以来さまざまな生物の相互干渉の結果である。ヒトというのも特別に浮き上がった存在なのではなく、当然それらの生物の1つと考えるべきであろう。であるならば、外来種を輸入したというのもヒトという生物の行動であり、ある種の生物が絶滅するほどに捕獲しつくしたのもヒトという生物の行動と考えるべきなのではないだろうか。ということは、その結果その国の固有種が駆逐されたとしても、ある希少種が絶滅したとしても、地球上の生物の変遷の歴史の中では特に不思議なことではなく、一生物種に過ぎないヒトが、他の種の生物が滅びないようにとシャカリキになることのほうが異常というかおこがましい行為なのではないか。それは神の領域の行いなんじゃないだろうかと思うのだ。いかがなものだろうか。(2005.5.17) |