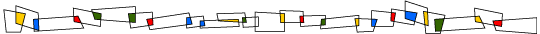|
第十四巻(第百三十一段〜第百四十段) |
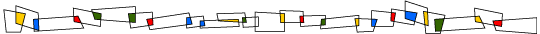
 |
第百三十一段 |
君は気づいているだろうか。プルトップ星人の存在に・・・。暑い暑い、プシュー!ゴクゴク、プハアー!ポイ!その陰でひそかにプルトップ星人は笑っている。そこでもここでもあそこでも、おそらくは世界中に今、ひそかにプルトップ星人は増殖している。店に、街角に、ゴミ箱に・・・プルトップ星人があふれている。そして、彼らはいつも笑っているのだ。缶ジュースを飲み終わった後、プルトップをクニクニしてごらん。きっと君もプルトップ星人に会うことができるだろう。(2005.5.24) |
 |
第百三十二段 |

夏の夕方、昔ながらの銭湯のがらんとした脱衣所は、とてもくつろいだ空気に満たされている。女湯のほうから、おばあさんたちの、見本のようなようなゆったりした世間話が聞こえてくる。声の感じから想像するに、もう70歳はとっくに超えているかんじだ。 |
 |
第百三十三段 |

曇天をついて、東に向かってひた走る。天気予報はあまりよくない。いつまで天気がもつか、それが気がかりだ。この夏の前半はとても忙しくて、ちょっとゆっくりしたい気もあったのだが、やはり年に1度は体におもいっきり風を通さないと化石になってしまいそうになる。豊科ICで高速を降り、R144を走る。適度なコーナーに身を任せ、ゆっくりと高度を上げていく。青木峠を越え、やがて山間の田沢温泉に到着。素朴でこじんまりした温泉だ。ますや旅館は木造3階建ての古い風情のある旅館である。かつては島崎藤村もこの宿に滞在し、詩想を練ったそうだ。黒光りした廊下や階段をぎしぎしと歩き、3階の6畳の部屋に案内される。障子を開け放つと、とても見晴らしがいい。田舎の親戚の家に来ているような感じがする部屋だ。温泉でゆっくり手足を伸ばし、部屋に戻って柱にもたれて、見るともなしに外に目をやっていた。涼しい。ウグイスの声、ぱたぱたと階下の廊下を走る小さな子の足音、少しずつせまる夕方の気配・・・なんともいえない懐かしさに包まれる。頭の中と外の区別がふと無くなるような不思議な心地よさ。ずーっと昔、子どもの頃の夏休みはこんな風であったような気がする。つい、うとうとしたのだろうか、気がつけば部屋の中はずいぶんうす暗くなって、ちょうど夕食が運ばれてくるところだった。 |
 |
第百三十四段 |

雨の音が聞こえる。「あーやっぱり降ってるなあ・・・」と思いつつ徐々に目が覚めてくる。携帯のアラーム以外の音で目を覚ますのは久しぶりだ。外はしっかりした雨。あきらめてゆっくりするか・・・と温泉に浸かる。朝風呂は気持ちよい。よすぎる。先人の戒めどおりだ。そのうち、気のせいか空がずいぶん明るくなってきた。お、やんだ!朝食もそこそこに出発した。上田から真田、嬬恋を経て浅間山麓を走る。さすがに浅間山は雲に隠れて見えなかったが、いつ来ても気持ちのよい道だ。右上がりの山麓の広がりを北から南へ一直線に切るようにスコーンと走り、昼過ぎに軽井沢着。旧道の緑を楽しみながらゆっくり走る。人は少なく、別荘あり、テニスコートあり、おしゃれなレストランありで、思わず天地真理の歌(かなり古!)が頭の中を流れた。遅めの、はるかに予想を超えた高い昼食(やられた)の後、碓氷軽井沢ICから高速に乗る。恵那でとうとう雨になった。すごく運転のうまいトラックに出会い、ずっとその後を走る。ほんまにうまい。力の抜けたというか、マイペースなのにとても自然で速い。これがプロの走りか!と感心した。おかげで予定よりずっと早く京都東ICに着いた。雨もやみ、京都の夜もなんだか秋っぽい。 |
 |
第百三十五段 |
|
「お父ちゃんが死んだらな」とずいぶん昔、まだ元気で大きかった頃の父は言った。「命日とかお彼岸とかはどうでもええから。お盆にな、15日にな、年に1回墓参りに来てくれたらええからな。」その頃は自分も子どもで、父の死なんてことにまるで現実味がなかったのでそんなに気にも留めなかった。父は無口で、会社から帰ると寝るまでずっとテレビを見ていて、そのくせ子どもには自由に見せてくれず、夜更かしをしているとしかる人だった。長いシベリア抑留生活を思い出すからと、戦争映画は見たがらなかった。几帳面で家のあちこちを直したり自転車を磨いたりすることを趣味のようにしていた。そんな父も18年前、胃癌であっけなく死んでしまった。小さく小さくなって、枯れるように死んでしまった。そうなってみると、思い出すのはあの約束。父と交わした唯一の約束。せめてこれを守ってやることぐらいしか今となってはできることはない。何かを供えたりすることは無意味だと骨を拾ったときに感じたから、ただ、年に1回そこへ行く。今日も行った。おそらく来年も。(2005.8.15) |
 |
第百三十六段 |
|
夏の盛りのある土曜日の夜、コザのとあるライブハウスにいた。入り口には巨漢のアメリカ人がどっかり座って「ゴヒャクエンネ」とチケットを切ってくれる。客はほぼ100%米兵とガールフレンドで、耳をつんざくハードロックの洪水の中で彼らはビール瓶を片手に笑い、叫び、飛び跳ね、語り合い、肩を抱き合い、右手を突き上げて歌う。これでもかというぐらいはじける。あきれるぐらいに。すべてをリセットするかのように。それが彼らの週末。しかし考えてみれば彼らには月曜日にはイラク行きの命令が来るかもしれないのだ。平和な日本の中の非日常の一瞬。いつも黒々と大きな口を開けている死の世界につながる一瞬。彼らにはその一瞬しかないのかもしれない。(2005.8.29) |
 |
第百三十七段 |
盆を過ぎた頃から、うそのように夜が涼しくなって、涼しいのはうれしいのだが妙に寂しい気分になる。気がつけば虫まで鳴き出す始末。夏が静かに、確実に終っていく。すっかり秋になってしまえば、それはそれでいいのだけれど、夏の終わりは本当につらくて、なにか無駄な抵抗をしたくなる。夏休みは、休みになる前がいちばん楽しくて、8月には入るとすこし気分にセピアがさし、盆を過ぎるとすっかりあせり始める。そういえば今年はツクツクボウシの声を聞いてない気がするが、ずんずん1日の終るのが早くなり、それこそ叫びだしたいような追い詰められた気持ちになり、地蔵盆に止めを刺される。ああ、もうだめだ。夏は戻ってこない。その上、こんな見事な秋の空まで見せられた日には・・・もう笑うしかない。(2005.8.29) |
 |
第百三十八段 |
十月も半ばになった土曜日、京阪の駅でふと見つけた顔見世の広告。「え、もう?」とショックを受けた。今年はずいぶん暑い日が続いていたのですっかり油断していた。もう今年が終ろうとしている。今年何をしただろうと振り返る。なにか今年を生きた証があるだろうか。なんとなく、その日その日をまるでカレンダーに×をつけるかのように生きてはこなかったろうか。まだまだ冬になっては困る。とりあえず半そでのTシャツで抵抗しているのだが・・・。 |
 |
第百三十九段 |
|
よく行くスーパー銭湯にミストサウナがあって、普段は入らないのだが、ふと入って1人でぼやーんとしていた。目が悪いもんだからぼやけている上にミストで、ぼやぼやの世界となる。ガラガラと入り口が開いて若い男が1人入ってきた。彼は目の前を通過して奥のほうへ入っていって湯気の中へ消えた。「えらい奥まであるんだ・・・」一瞬思ったが気にも留めず引き続きぼやーんとして、「さて出るか」と立ち上がってどこまで奥があるのかと見に行くと、すぐに壁があってそこで終わっていた。「ん?」彼はいったいどこへ消えたんだろう。土曜の午後のちょっとみすてりい。(2005.12.3) |
 |
第百四十段 |

「看護婦という名称には差別性がある、看護士にしまーす」と言われて久しい。ちょっと言い間違えると「看護士デス!」と訂正されたりする。保母も保育士、スチュワーデスもフライトアテンダントとかになった。でもなあ・・・と思うのだ。これって差別?病院に来るような心も体も弱ってる人にとって、「看護士さん」と言うのと「看護婦さん」と言うのでは、どちらがやさしく響くだろう?どちらが癒されるだろう?どちらが硬く、取っ付きにくい感じがするだろう?同じく、小さな子供たちにとって、あるいはその親にとって、「保育士さん」と「保母さん」はどちらがやさしく、あたたかく響くだろう。呼称を統一したから「はいOK!」というのは、あまりにも短絡的で表面的な発想ではないだろうか。むしろ差別をその程度のものと考えて処理することこそ差別的だ。患者や乳幼児の目線からの発想というのをもっと大切にすべきだと思うのだけどねえ。だって、呼称から性差を取り除くことがよいのなら、父さん母さんも親さん親さんになるし、兄さん姉さんも年上の子供さん年上の子供さん(兄弟姉妹もあかんからね)、爺さん婆さんも親の親さん、叔父さん叔母さんも親の同じ親から生まれた子供さん、甥姪はえーっと・・・もうわけわからん。差別と区別は違うのだから。そこんとこを考えとかないと本当に混乱する。学校現場の男女混合名簿なんて、その最たるものだ。(2006.1.7) |