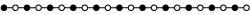|
第十五巻(第百四十一段〜第百五十段) |
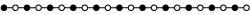
 |
第百四十一段 |

大阪は日本一歩行スピードが速い街らしい。確かにそのとおりだ。乗り換えのある大きな駅なんか、もう人に轢かれそうな気がする。車以上に気を使わないと車線変更できない。もう夏なんて歩いているだけでクタクタになる。そんな時に見つけたこの看板のなんと魅力的だったことか。入ってみると、看板どおりの落ち着いた、つまりなんの変哲もない喫茶店だった。(2006.8.15) |
 |
第百四十二段 |

大阪らしいというか、素朴な怒りにあふれたこの看板、どう考えても無理。気持ちはわかるんだけど、誰がどうやって遠くへ運ぶというのだろう?しかし「遠方」が効いたのか周囲には1台の車もなかった。(2006.8.15) |
 |
第百四十三段 |

ステーションマスターって・・・なんぼなんでも無理がある。駅長さん、なんかいやなことでもあったのだろうか。ちなみにこの張り紙は2週間ほどで撤去された。(2006.11.6) |
 |
第百四十四段 |

風呂上り、パジャマでぼーっとしているとピンポーンとチャイムが鳴った。外はいつの間にか雨になっている。いったい今頃誰だろうと思いつつドアを開ける。 |
 |
第百四十五段 |
妄想は続く・・・。 |
 |
第百四十六段 |
|
さらに続く妄想・・・。 |
 |
第百四十七段 |
|
主題歌まで作っちゃう。 |
 |
第百四十八段 |

恋と愛のオハナシ |
 |
第百四十九段 |
|
「七夕みたいに1年に1日のデートってどーよ」 |
 |
第百五十段 |
子どもの頃の夏休みの最大の楽しみは三重県の山深い親戚の家に遊びに行くことだった。そこはその頃の自分にとって、遠い遠いとっても遠いところで、およそ日常の生活とかけ離れた夢の世界であった。バスに1時間、単線の列車に1時間、トンネルを抜けるたびに深まりゆく山と渓谷、そしてディーゼル機関車の独特の匂いが、いやがおうでも旅の興奮の度合いを高めるのだった。列車を降り、さらに土煙を上げて走るバスに30分ほども揺られ、バス停から20分ほど坂を上ると、ようやくひなびた鳥居に辿り着く。そこからさらに道を下り川を渡り長い石段を上ると、うっそうとした林と山に抱かれるように、その家はあるのだった。いよいよ夢のような日々が始まるのだ。早朝からいとこたちとクワガタやカブトムシを取りに出かけ、濃い牛乳を飲み、谷川でカニを探し、縁側で昼寝をし、縁の下に蟻地獄を発見し、よろず屋へ買い物に出かけ、野球をし、かくれんぼをし、スイカを食べ・・・と、思いつく限りの遊びをしているうちに日は西に傾き、あたりはヒグラシの大合唱に包まれる。風呂上りの夕方はすっきりと涼しく、お釜で炊かれた夕食のおいしいこと!その後も花火をしたり、灯りに寄ってくる不思議な蛾に見とれたり、布団の上を転げまわったりしているうちに、いつしか眠りにつくのだった。しかし楽しい日々はあっという間に終わり、帰る日となってしまう。盛大に手を振るいとこたちはバスの窓にどんどん小さくなり、列車に、バスに乗り換えるにつれて、膨らんでいた夢も希望も夕日が沈むのに合わせるかのようにシューと音を立てるようにしぼんでいくのだった。夜、家についた瞬間、「ああ、今年の夏休みも終わったな」などと子供心にたそがれていたのが妙に懐かしい。(2007.8.17) |